一茶と言えば、“痩蛙まけるな一茶是にあり”とか “やれ打つな蝿が手を擦り足をする”と言った、癒されるような表現に代表される、穏やかな人柄の俳人を想像していたが、この本を読んで、自分の想像が間違っていたことを痛感した。
一茶は信州の山奥の百姓の長男だが、継母のせつに冷たく扱われ江戸に奉公に行くことになるが、俳句の集まりに顔を出すうちにその才能に目をかけられ、俳諧人の道を進むことになる。江戸で偉くなり、宗匠として一家を構えることを目指すが、運に恵まれず、貧しい旅の俳諧人で人生を終わりそうになるのだが、そのまま江戸に残り夢を追及するのか、田舎に帰って暮らすのか大いに悩む。田舎には冷たかった継母と異母弟の仙六が家を仕切っており、醜い相続争いをせねばならなかった。
辛い・貧しい生活の為に、貧乏な句や世間に開き直った句、また自分を嘲るような句を詠むようになってきたが、田舎に帰り、50過ぎになって、やっと嫁をもらう事が出来、人並みの幸せを掴むことも出来た。その結果、読む句も丸みを帯びた穏やかな句が増えてきた。子も出来、幸せな生活が始まったが、子供は次々に幼くして死んでいき、最後には嫁の菊も病気で死んでしまう。その後恥をしのんで、後妻を紹介してもらうが、一人目とは3か月で離縁される。それでも、その後20歳近く年の違う後妻が来てくれて、幸せな生活が始まりだしたところで死んでしまう。
世渡りは上手だが、人を信じず、落ち込んで行く自分に愛想を尽かしながらも、出世欲は強く、暗い人生を送ることになってしまった。人間の厭らしさを人一倍持った一茶が苦悩をしながら、貧しい生活の中で、一途に俳句を作り続けた俳諧人の一生の物語りである。人間の厭らしさ、一途さが混ざり合った、色々考えさせられる話しであった。
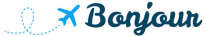
コメントをお書きください